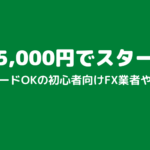FX初心者に選ばれる優良FX会社を徹底比較!スプレッド(手数料)やお得な限定キャンペーン、人気のスマホアプリなどジャンル別で調査した人気ランキングも掲載中!
FXで勝ちたいなら一番初めの口座選びが大切です!
※この記事はアフィリエイト広告を利用しています
おすすめFX業者 比較表
| 会社 |  |
 |
 |
 |
| デモ口座 | × | ◯ | ◯ | 〇 |
| 取引単位 | 1通貨 | 1,000通貨 | 1,000通貨 | 1,000通貨 |
| 通貨ペア数 | 20通貨 | 20通貨 | 51通貨 | 34通貨 |
| 取引開始まで | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 |
| キャッシュバック | 最大100万円 | 最大55万円 | 最大56,000円 | 最大100万円 |
| 詳細 |

fa-check-circle高スワップを提供
fa-check-circle取引単位が1000通貨単位で画面も見やすく初心者向き
| 通貨ペア数 | 取引通貨単位 | デモ口座 | キャッシュバック |
|---|---|---|---|
| 24通貨ペア | 1,000通貨 | 〇 | 最大550,000円 |
![]()
FX初心者ということもあり、とにかく取引画面の見やすさと分かりやすさを重視してを選びました。1000通貨単位で取引可能で種類が多いのも魅力だとは思います。
![]()
大手グループ関係のサービスなので、安心できます。例えば、万が一問題があって資金が流出した場合でも、必ずお金を保証してくれるという他サービスにはない安心感があります。
![]()
黒い背景に色分けされたグラフできれいにチャートを描いており、画面の大きさに関係なく視認性が優れている点は評価します。

fa-check-circle高水準なスワップポイント
fa-check-circle取引コストが安い
| 通貨ペア数 | 取引通貨単位 | デモ口座 | キャッシュバック |
|---|---|---|---|
| 20通貨ペア | 1,000通貨 | 〇 | 最大55万円 |
![]()
GMOという大手企業ならではの安心感があります。実際に知り合いでもGMOクリック証券の口座を開設して、FX取引を始めた人がいます。知っている人が使っているFX会社なので、安心して取引が続けられます。
![]()
基本的にはメインで利用するため用のFX会社だと感じています。
スピーディーな取引が出来る事やチャートツールの使いやすさ、数多くのテクニカル指標だけでも業界トップクラスと断言できます。
![]()
もっとも優れているのが約定力の高さです。狙った価格での売買ができるので、裁量トレードの際にはここのメインになっています。約定力が弱いFX会社だと狙った価格での売買注文が通らないこともありますが、ここはそのようなことが今までありません。

fa-check-circleスキャルピングトレードができる
fa-check-circle約定スピードが非常に早い
| 通貨ペア数 | 取引通貨単位 | デモ口座 | キャッシュバック |
|---|---|---|---|
| 51通貨ペア | 1,000通貨 | 〇 | 最大56,000円 |
![]()
ヒロセ通商はまだやり始めて数ヶ月ですが、比較的簡単で気軽にできるところが気に入っています。取引の量が増えるとキャッシュバックやその時に開催しているキャンペーンで食品などいろいろと物がもらえるのでお得な気持ちになります。
![]()
一番気に入っているのは、スキャルピングトレードができるところです。他社ではスキャルピングトレードを認めていないところもありますが、LION FXではスキャルピングを公式に認めているので安心してスキャルピングができるところに満足しています。
![]()
約定スピードが非常に早く、急激な価格変動があってもすぐに約定できることが多いので、損失が大きくなりませんでした。また、数少ないスキャルピングができる会社なので、スキャルピングでも利益を出すことができました。

fa-check-circle有名企業ならでは信頼感
fa-check-circle広がりにくく安定したスプレッド
| 通貨ペア数 | 取引通貨単位 | デモ口座 | キャッシュバック |
|---|---|---|---|
| 21通貨ペア | 10,000通貨 | 〇 | 最大30万円 |
![]()
本当に使いやすいと思った。
ボタン操作もわかりすく、設定もしやすかったので特に困ったことはなかった。アプリを色々と研究されており、1秒を争う世界で戦ったもらえるよう開発されたんだろうと企業努力がうかがえます。
![]()
DMM.comはテレビやネットでよく見かける会社なので、運営が他の会社よりもしっかりしているというのが第一印象でした。実際に利用した感想ですが、問い合わせへの回答もスムーズで安心感があります。
![]()
違う証券会社から乗り換えましたが、PCでのチャートツールの使いやすさに驚きました。わざわざ操作方法を調べたり、覚えたりする必要もなく直感的に操作する事が出来ます。また、知りたい情報をすぐに表示できるのでストレスが溜まる事もありません。

fa-check-circle中・上級にも利用される充実したツール
fa-check-circle豊富なマーケット&投資情報
キャンペーン対象期間:口座開設月から翌月末まで
| 通貨ペア数 | 取引通貨単位 | デモ口座 | キャッシュバック |
|---|---|---|---|
| 30通貨ペア | 1,000通貨 ロシアルーブル/円のみ10,000通貨 |
〇 | 最大100万2,000円 |
キャンペーン対象期間:口座開設月から翌月末まで
![]()
外為どっとコムは低スプレッドで安定していているのでとても取引がしやすいと感じています。セミナーや解説動画が分かりやすいので、初めてFXをする人にはとても勉強になると思います。
![]()
はじめてのFXで、外為どっとコムを選びました。基本スマホアプリでしかトレードしないのですが、はじめの頃もアプリの使用感が良かったのでスムーズにトレードすることができました。情報過多と言うわけでもなく、使い勝手がいいです。
![]()
テクニカルツールの「ぴたんこテクニカル」がとにかく使いやすくて、これを使いたくて口座を開設しました。このツールは、お天気シグナルとみらい予測チャートが便利です。このツールを使うとより勝てる確率が上がるので、トレードには心強いツールです。
FX「外国為替証拠金取引」とは?
FXとは「Foreign Exchange」の略で、日本語の正式名称は「外国為替証拠金取引」です。日本語にされても英語が漢字になっただけで、あまりピンとこない人も多いと思います。そこで「①外国為替」と「②証拠金取引」の二つに分けて説明していきます。
「外国為替」とは?
まずは「外国為替」です。世界にはさまざまな通貨があります。日本でみなさんが使用している通貨は円ですが、アメリアに行けばドルを使い、ヨーロッパに行けばユーロを使うことになります。そのため海外旅行に行く時は、円をドルやユーロに交換する必要があります。この通貨の交換(売買)が外国為替です。そして通貨を交換する際に必要になってくるのが「外国為替レート」です。
「外国為替レート」は通貨の交換比率のことで、よくニュースなどで耳にする1ドル=100円のことです。例えば、日本円でドルを買いたいとします。この時の為替レートが1ドル=110円だったとすると、1ドルを手にするのに110円が必要になります。外国為替とは、為替レートを使用して行う通貨の交換(売買)と覚えておくといいでしょう。

「証拠金取引」とは?
FXで取引する際には、通貨の売買のたびに代金を支払うことは基本的にしません。その代わりに、FXでは、決済した時に売買によって生まれた利益をもらい、損失があれば支払うことになります。このような取引のことを「差金決済」と言います。
先ほど少しだけ触れましたが、この「差金決済」の場合、取引で損失が出ても決済できるようにあらかじめ一定額の資金を預けて置く必要があります。この預けた資金のことを「証拠金」と呼び、この資金を使って取引するため「証拠金取引」と言われます。
FXの正式名称である「外国為替証拠金取引」がどのようなものかご理解いただけたでしょうか?とにかく始めてからFXについて勉強するのもいいかもしれませんが、事前にFXに関するさまざまな情報を集めていても損はありません。当サイトではFXに関する知識はもちろん、各FX業者の情報や特徴(スプレッド、通貨ペア数、取引単位、情報量、キャンペーン等)を独自で調査し、徹底的に比較して紹介しています。ぜひ有効活用してみてください。
副業に最適なFX!スキマ時間を活用して副収入を得る人も
忙しいサラリーマンや主婦の方で、副収入を得るためにFXを始める人が年々増えてきています。
FXが選ばれる理由はその特徴と関係しています。副業を始める人は以前に比べ多くなりましたが、その種類としては記事の執筆やハンドメイド、YouTubeなど、始めるには少しまとまった時間が必要になるものが多いです。
そんな中でFXは、基本的に平日24時間いつでも取引できます。というのも、FXは既に説明した通り、さまざまな国の通貨を扱うため世界中で外国為替市場が開いています。そのため通勤時間や寝る前など、それぞれのライフスタイルに合わせて取引することができます。イメージしにくいという方は、サラリーマンがスキマ時間でFXをする場合を想定した下記の記事「FX初心者が月20万稼ぐには?1日のスケジュール&トレード手法」をご覧ください。

少額で始められるから安心
そしてもう一つのFXの特徴は、少額で始められることでしょう。投資と聞くとどうしても多額の資金が必要だと思いがちですが、FX業者の中には5,000円から始められるとことも多くあります。当サイトがおすすめする少額でFXを始められる業者は「松井証券のFX」です。
また少額でFXを始めたい方はこちらの「予算5,000円でスタート!少額トレードOKの初心者向けFX業者や取引方法」でトレード手法を詳しく解説しているのでご覧ください。少額トレードの場合、仮に損失を出した場合でも少額で済むため、まずは少ない資金で始めてトレードの実践経験を積んでから、より大きい金額で取引する人が多いです。
充実したスマホアプリでいつでもどこでもFX
さらにFXを始める人の増加している要因の1つに、スマートフォンへの対応もあります。今ではほとんどの人の生活に欠かせないものとなったスマートフォン。
スマホがあればパソコンはいらないという人もいるのではないでしょうか?
もちろんほとんどのFX業者でiPhone・AndroidといったスマートフォンやiPad等のタブレット端末にも対応。また、モバイル用アプリの機能の改善を積極的に取り組み、これまでより機能が充実しているとされていたパソコンでの取引とほぼ同様の環境で取引できりるようになっています。外出先でも簡単にチャートを開いたりトレードしたりすることができるようになり、最近FXを始めたという人の中には、スマホでしか取引したことがないとう人も少なくないでしょう。
外国為替のおもしろい・楽しいところとは?
FXをやっていておもしろい・楽しいと感じることといえば、実際に自分が行ったトレードで利益が出た時ですよね。稼ぐ為にたくさん勉強をして、デモ口座などで練習を重ねるのが一般的なFXの始め方です。
また、どうやって取引すれば勝てるようになるんだろう?ということを考えながら経済ニュースや市場イベントの情報を収集することにより、世界情勢に目を向ける機会が増えることになります。 すると自然と知識がついてきて、周りからの評価が上がることも。
各FX業者では豊富な情報を得ることができるので、情報収集目的のみでFX口座を開設して活用している人もいます。優良コンテンツを提供している業者は数多くあるので、各業者の情報コンテンツを比較してから口座開設すると良いでしょう。
FX関連のセミナーを無料開催している業者もあります。そういった場に参加することでセミナーに参加している方との交流が広がり、FXを始めなければ出会えなかった方と友人関係が築けたりもします。
一人じゃ心細かった人も、FX仲間同士であれやこれやと話し合う機会があるだけで、もっと極めたい!もっと稼ぎたい!と楽しんでFXが出来ている事が実際に多くあるようです。
FXに関するよくある質問
ここまで読んでFXを始めてみたいという思った方もいると思います。そこでここからは、FX取引を始める前に知っておきたい基礎知識や用語などをQ&A形式で紹介します。もちろん全ては網羅できないので、気になった用語は自分で調べてみてください。
FXはどうやって始めるの?始めるのにいくら必要?
FX取引を始めるためには、FX業者で専用の口座を開設する必要があります。当サイトでも紹介しているようにさまざまなFX業者がサービスを提供していて、それぞれ特徴が違います。それぞれの業者によって異なりますが、口座開設は最短で即日、場合によっては2~3日程度必要になります。
FX業者の特徴の違いの一つに取引単位があります。大きく「1,000通貨」と「10,000通貨」に分かれています。取引単位が「1,000通貨」の業者を選べば、為替の状況にもよりますが5,000円からでも取引できます。これからFXを始める人には、「1,000通貨」で取引できる業者で比較的ローリスクでトレードして経験を積むことをおすすめします。
1,000通貨ってどういう意味?
FX取引では基本的にまとめて売買されます。そのため取引の単位が「1,000通貨」や「10,000通貨」となっています。例えばドル円を1,000通貨取引した場合は、1000ドルを取引することになり、1ドル100円だと10万円の取引となります。これが取引単位1万通貨だと1万ドル=100万円の取引になるのが分かると思います。
そしてレバレッジをかけることができるので10万円や100万円といった資金を準備する必要もなく、少額から取引が可能になります。

レバレッジとは?
レバレッジはもともと「てこ」を意味しますが、FXなどの取引においては「少ない資金で大きな金額の取引ができること」といったことになります。FXでは、金融庁が定めたルールにより最大25倍のレバレッジをかけて取引することができます。それでは1ドル100円の時、25倍のレバレッジで1,000通貨取引しようとした場合、証拠金はいくら必要になるでしょうか?
正解は4,000円です。式は下記のようになります。
10万円(100円×1000通貨)=25倍×4000円(証拠金)。
レバレッジを大きくして取引する場合は、その分リスクも大きくなることを理解しておきましょう。そのため初心者の方には、2~3倍で取引を始めてみることをおすすめします。
FX業者を比較するときのポイント
これからFXを始めようとして、どのFX業者で口座を開設すべきか悩んでいる人もいると思います。そこで、比較する際に注意しておきたい基本的な3つのポイントを紹介します。
まずFX業者を比較する際に大切なのが「①最小取引単位」です。FX未経験の初心者の方が最初に口座開設する場合におすすめしたのが1,000通貨から取引できる業者です。
上記の「FXに関するよくある質問」のセクションで、FXでは取引通貨単位があることは説明しました。取引通貨単位が1,000通貨の業者だと、少ない資金でもFXを始めることができます。もちろん1,000通貨だと利益は小さくなってしまいますがその分失敗した時の損失も小さくて済むため、まだトレードに慣れていない初心者の方にはおすすめの取引所と言えます。
注意しておきたい2つ目のポイントは、「②通貨ペア」です。FX業者によってこの通貨ペアは本当にさまざまです。そのため、必ずしも提供する通貨ペアが多いFX業者が自分に合っているとも言い切れません。そのため、自分がどの通貨ペアを取引したいのかを明確にしておくようにしましょう。
3つ目のポイントが「③スプレッド」です。実際にFXを取引すると「売値(BID)」「買値(ASK)」の2つの価格があり、この真ん中に「0.3」といった価格差が表示されています。この価格差のことをスプレッドと呼びます。スプレッドは実質的にFX会社に支払う手数料とも言えます。そのため、ご自身が取引する予定の通貨ペアのスプレッドはどうかFX業者を比較してみるのがいいでしょう。
その他にもFX業者を選ぶ際に、自動売買機能の「システムトレード」が使える口座かどうか、ニュース配信の数、金利差を利用して利益を狙うスワップの大きさなど、比較できることはさまざまです。ただし初心者の方は、とにかく実際にトレードをしながら勉強することも大切だと言われています。気になるFX会社がいつからある場合は、とりあえず1社を選んで口座開設の申請をしてみることをおすすめします。
FXを始めるにあたって一番最初に決めなければならないのが使用するFX業者を選ぶことなので、「FXに挑戦したい!」「どこの会社にしたらいいのかわからない!」と迷っている人はぜひ当サイトを活用してください!
勝つための資産運用はFX業者選びから始まります!
調査概要は下記になります。
【調査概要】
調査目的:FX取引に利用している会社、ユーザー分布の調査
母集団:投資に知識、興味のあるインターネットユーザー
調査対象地域:日本国内(海外からのアクセスは除外)
調査対象者:ユーザー アンケート結果はこちら